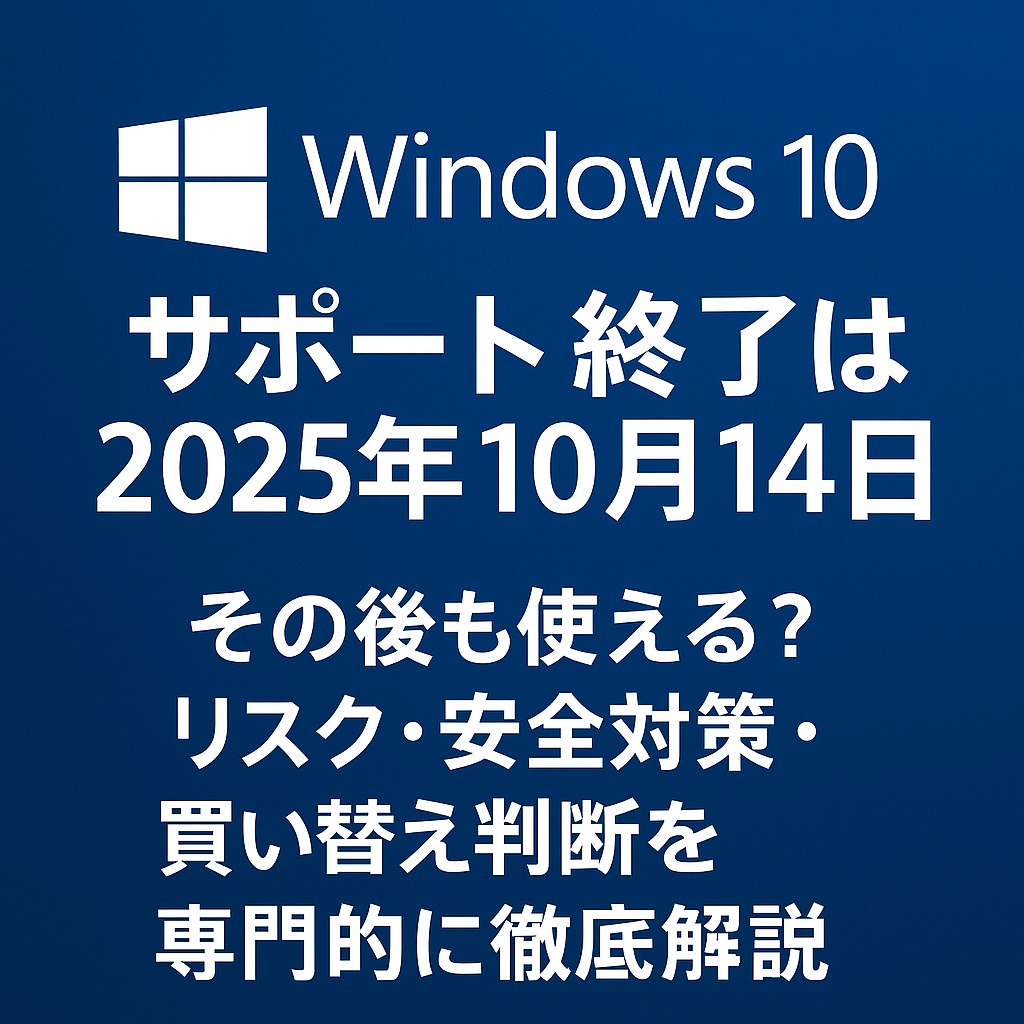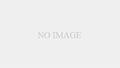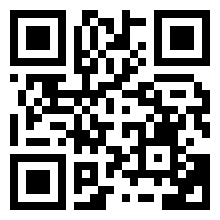2025年10月14日──。この日付を、あなたは覚えているだろうか。
Windows10の公式サポートが終了する日だ。世界で数億台が今も稼働している「10」の時計が、静かに止まる。その瞬間から、ウイルス対策の盾は薄れ、脆弱性の修正は止まり、あなたのPCは“未来の攻撃”にさらされることになる。
「でも、まだ動くんでしょ?」「買い替えはもったいない」──そう考える人は多い。確かに、Windows10は2025年10月15日になっても起動する。WordもExcelも、昨日と同じように開く。だが、その裏で起きているのは“見えない崩壊”だ。セキュリティの穴、更新停止、アプリ非対応。気づいた時には、メールが乗っ取られ、データが流出していた──そんな事例は、Windows7の終了時にも現実に起きた。
Microsoftの公式発表によれば、サポート終了後はセキュリティ更新・品質更新・テクニカルサポートの提供がすべて終了する(Microsoft公式/最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。これは単なる「終了のお知らせ」ではない。世界中のハッカーが「更新の止まったOS」を狙い撃ちにし始める“開戦宣言”でもある。
では、サポート終了後のWindows10は本当に使えなくなるのか? それとも「延命」「アップグレード」「買い替え」で道はあるのか?
本記事では、元通信社アナリストとして、そしてメディアリテラシーの講師として、あなたのパソコンが直面する現実をデータと一次情報に基づいて徹底解剖する。
・OSサポート終了の本当の意味 ・一般ユーザーに降りかかるリスクと被害の実例 ・買い替えが必要な人/延命できる人の判断基準 ・職業・用途別のリスク格差 ・そして、今日からできる“現実的な安全策”
いま、この記事を読むかどうかで、あなたのPCの“余命”が変わる。
「まだ動く」ことに安心してはいけない。問題は、“守られなくなる”ことだ。
──この先の章で、あなたのWindows10がどこまで安全に生き延びられるか、その全貌を明らかにしよう。
Windows10サポート終了の正式日程と「終了後も動く」の真実
「2025年10月14日」──それは、あなたのパソコンの“安全神話”が終わる日だ。
でも、終わるのは「電源」ではない。
むしろ怖いのは、電源は入るのに、守りが消えるという現実だ。
ここでは、Microsoftの一次情報と公的発表を基に、サポート終了の意味を冷静かつ徹底的に解き明かす。
1-1. 正式終了日は2025年10月14日──Microsoft公式発表が明示
まず事実を確認しよう。
Microsoftは公式サイトで、Windows10のサポート終了日を明確に「2025年10月14日(JST)」と発表している。
この発表は、Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Educationのすべてのエディションに共通して適用される。
参考:Microsoft公式サポート情報(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
つまり、2025年10月15日以降にWindows10を起動しても、セキュリティ更新プログラム(Security Update)や品質更新(Quality Update)は一切届かない。
OSそのものは起動する。
だが、更新の仕組みが止まる──これは「機能が死ぬ」のではなく、「防御力が失われる」という意味だ。
1-2. 「使えなくなる」と「使い続ける」はまったく別の話
多くの人が誤解している。
サポート終了=動かなくなる、ではない。
実際、Microsoftは「Windows10はサポート終了後も起動し、ライセンスも無効化されない」と明言している。
つまり、WordもExcelも動作する。
しかし、セキュリティ修正が行われないため、OSの内部に新しい脆弱性が発見されても修復されない。
これが「ゾンビOS」と呼ばれる状態だ。
動いてはいるが、攻撃者の標的になりやすく、防御が更新されない。
例えるなら、夜の街をドアの鍵を壊したまま歩くようなものだ。
あなたが被害者になるだけでなく、ウイルス感染によって他人のPCに攻撃を仕掛けてしまう可能性すらある。
この“伝染性リスク”が、サポート終了後に最も警戒される理由だ。
1-3. Microsoftが用意する「延命策」──拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)
「今すぐ買い替えは難しい」という人にとって、救済策は存在する。
それが「Extended Security Updates(拡張セキュリティ更新プログラム:ESU)」だ。
ESUとは、サポート終了後も一定期間、重要なセキュリティパッチを有料で受け取れる仕組みである。
これは、Windows7終了時にも提供されていた制度で、主に企業向けに販売された。
Microsoftは2024年12月に、Windows10向けESUを個人ユーザーにも提供する方針を発表している(参照:Windows Experience Blog/最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
ただし、このESUは「セキュリティ更新のみ」であり、機能追加・品質改善・互換性対応は含まれない。
つまり、“時間を稼ぐ”ことはできても、“未来を守る”ことはできない。
加えて、費用が年単位で発生する見込みであり、長期的には新しいPCを購入するより高くつく可能性もある。
結論として、ESUは「移行の猶予期間を確保するための保険」であり、恒久的な解決策ではない。
1-4. いま何が止まり、何が動くのか──終了後の「機能別影響表」
ここで一目で理解できるように、サポート終了後に“止まるもの/動くもの”を整理しておこう。
| 項目 | 終了後の状態 | 備考 |
|---|---|---|
| Windows起動・ライセンス | 動作継続 | OSは起動しライセンスも有効。ただし更新停止。 |
| セキュリティ更新 | 停止(ESU契約者のみ継続) | 新しい脆弱性に未対応。 |
| 品質更新(バグ修正) | 停止 | 不具合・クラッシュなどが修正されない。 |
| テクニカルサポート | 終了 | Microsoftサポート窓口での対応不可。 |
| アプリ互換性 | 徐々に低下 | 新しいOfficeやブラウザが非対応になる可能性。 |
| オンライン認証・サービス接続 | 一部影響 | 将来的にMicrosoftアカウント連携で問題発生の可能性。 |
| ドライバー更新 | 停止または制限 | 新しいハードウェアへの対応が打ち切られる。 |
この表を見ると一目瞭然だ。
Windows10は「動く」──しかし「守られない」。
そして時間が経つほど、“動作”よりも“危険”が上回っていく。
1-5. なぜMicrosoftは「10年ルール」で見切りをつけるのか
Microsoftは、Windows10を「最後のWindows」と呼んでいた時期がある。
しかし実際には、テクノロジーとセキュリティ要件の進化が速すぎた。
とくに近年は、ハードウェアレベルでのセキュリティ(TPM 2.0、Secure Bootなど)が標準化され、古い構造のOSでは追いつけなくなっている。
Microsoftの公式説明によると、Windows11は「ゼロトラスト時代」に対応するため、TPM 2.0やハードウェア暗号化を必須要件にしている。
参考:Microsoft Docs – Windows 11 要件(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
つまり、サポート終了の背景には「古いOSを切ることで、より安全な新OSへの移行を促す」という企業戦略と社会的要請がある。
セキュリティを更新し続けるコストよりも、次世代OSに投資する方が効率的──それがMicrosoftの合理的判断なのだ。
1-6. まとめ:あなたのWindows10が直面する現実
- 2025年10月14日以降、Windows10は更新が止まる。
- OSは動作するが、守られない「ゾンビ状態」になる。
- ESUによる延命は可能だが、あくまで一時的な“延命措置”。
- MicrosoftはTPM2.0時代のセキュリティ基準へ完全移行中。
- 放置はリスクの連鎖を招く──早めの対策が唯一の防御線。
──ここまでが事実、そして“現実”だ。
次章では、この「守られなくなる」現実がどのようなリスクとして日常生活に影響するのか。
サポート終了後に待ち受ける7つのリスクを、実際の事例とともに分析していこう。
サポート終了後に起こること──一般ユーザーにも影響する7つのリスク
「更新が止まるだけでしょ?」──そう思っている人ほど危ない。
Windows10のサポート終了は、あなたのPCの“防壁”を静かに外していく。
しかも、その変化は1日では起きない。
時間をかけて、じわじわと侵食する。
ここでは、Microsoftや専門機関の公開情報をもとに、一般ユーザーにも直撃する7つの具体的なリスクを明示する。
2-1. セキュリティ更新の停止──新たな脆弱性が放置される
最大の問題は、サポート終了=セキュリティ修正が止まることだ。
Microsoftは毎月「Patch Tuesday」と呼ばれる定期アップデートで、発見された脆弱性(セキュリティホール)を修正している。
しかし、2025年10月14日をもって、この更新サイクルはWindows10に対して終了する。
つまり、それ以降に見つかった脆弱性は永遠に放置される。
実際、Windows7のサポート終了後には、脆弱性「BlueKeep(CVE-2019-0708)」が放置され、ランサムウェア感染が世界的に拡大した。
参考:Microsoft Security Response Center(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
ウイルス対策ソフトだけでは、この種のOSレベルの脆弱性を防げない。
理由は簡単。ウイルス対策ソフトは「既知の攻撃」を防ぐが、「OS内部の欠陥そのもの」を修正することはできないからだ。
2-2. ソフト・アプリの非対応化──「動かない」よりも「更新できない」
時間の経過とともに、ソフトウェア開発会社はWindows10対応を打ち切る。
たとえば、Microsoft 365(クラウド版Office)はWindows11を基準に最適化されており、古いOSでは更新や同期が不安定になる。
また、Adobe製品やZoom、Teamsなども順次「Windows11推奨」に移行中だ。
サポート外のOSでは、エラーが出ても開発元が責任を取らないケースが増える。
「動くけど保証されない」──これが最も厄介な中間地帯だ。
2-3. ブラウザと通信規格の更新停止──“安全なWeb”にアクセスできなくなる
インターネットの世界は、OS以上に変化が速い。
暗号化通信(TLS 1.3など)やブラウザのセキュリティ規格は年々更新されており、古いOSではこれらの規格に対応できなくなる。
実際、Google Chromeはすでに「Windows7」「Windows8.1」のサポートを2023年2月で終了した。
出典:Google Chromeヘルプ(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
Windows10が同様の扱いを受けるのは時間の問題だ。
ブラウザが更新されなくなれば、HTTPSサイトでの認証エラー、Webアプリの表示崩れ、動画再生の不具合などが発生する。
つまり、ネットを「見る」「調べる」「買う」といった日常的な行動が、少しずつ不安定になっていく。
2-4. 周辺機器の互換性問題──「印刷できない」「USBが認識されない」
WindowsはOS更新によって、プリンタやスキャナ、カメラなどの「ドライバー(機器を動かすためのソフト)」も最適化している。
サポート終了後は、これらのドライバー更新が停止する。
結果として、「新しいプリンタを買ったのに接続できない」「USBが認識されない」といったトラブルが増加する。
特に、業務用プリンタや特殊デバイス(会計機器など)はドライバー依存度が高く、OS更新が止まると一気に使えなくなる可能性がある。
2-5. Microsoftサポート終了──トラブル発生時に“頼れる先”がない
サポート終了後、Microsoftの技術サポート窓口ではWindows10の問題を受け付けなくなる。
つまり、動作トラブルや不具合が発生しても、公式な修正パッチや問い合わせ対応が得られない。
サポート外のOSでの不具合は「自己責任」扱いになる。
これにより、修理業者や非公式フォーラムへの依存が増え、結果的にトラブル解決のコストも上昇する。
「困った時に誰も助けてくれない」──これがサポート終了の現実だ。
2-6. 情報セキュリティ・法令リスク──企業利用では“使用禁止レベル”
もしあなたが会社員やフリーランスとして仕事でPCを使っているなら、ここは特に重要だ。
多くの企業は「サポート終了OSの使用を禁止」する情報セキュリティ規程を設けている。
これは、サポート外OSを社内ネットワークに接続すること自体が、情報漏洩リスクを増大させるからだ。
また、個人情報保護法や契約上のセキュリティ要件にも抵触する可能性がある。
経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」でも、OSのサポート状況を維持することは経営者の責務として明記されている。
参考:経済産業省 サイバーセキュリティ経営ガイドライン(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
つまり、業務でWindows10を使い続けることは、「コスト削減」ではなく「リスク拡大」でしかないのだ。
2-7. パフォーマンス・安定性の低下──古いOSは“腐る”
サポート終了後は、細かなバグ修正やシステム最適化も行われなくなる。
結果、アプリがクラッシュしたり、更新が失敗したり、動作が極端に遅くなるケースが増える。
特に長年アップデートを重ねたPCでは、OS内部のレジストリやキャッシュが肥大化しており、安定性が低下する傾向にある。
これにより、「使えるけど不安定」=最もストレスフルな状態になる。
つまり、機能は残っても“信頼性”が失われる。
2-8. まとめ──サポート終了後は“静かな崩壊”が始まる
- ウイルス感染や情報漏洩など、セキュリティの穴が放置される。
- アプリやブラウザの更新停止により、徐々に「使えない」領域が広がる。
- 周辺機器・クラウド・業務システムとの互換性が低下する。
- Microsoftも他社も、もはやあなたのPCを守らない。
つまり、Windows10は「即死」ではなく「静かに崩壊するOS」になる。
いま行動しないことが、最も危険な選択だ。
次章では、Word/Excel/YouTubeなど、一般ユーザーが日常的に使うサービスに具体的にどんな影響が出るのかを解き明かす。
あなたの“いつもの操作”が、ある日突然できなくなる──その理由を見ていこう。
Word・Excel・YouTubeなど一般ユーザーの日常利用に直撃する影響
「私は仕事で難しいことはしてない。WordとYouTubeくらいだから大丈夫」──そう思っているあなたほど、実はリスクの波に近い位置にいる。
Windows10のサポート終了は、専門職だけでなく、“普通の使い方をしている人”にも容赦なく影響を及ぼす。
ここでは、文書作成・動画視聴・ネット利用など、日常的な用途別にそのリスクを具体的に見ていく。
3-1. Word/Excel/PowerPoint──「動く」けれど「守られない」Office
まず最も多くの人が使うのがOffice(Word・Excel・PowerPoint)だ。
結論から言えば、Windows10サポート終了後もアプリ自体は開く。
文書の編集もできる。
だが問題は、その裏で行われる更新とクラウド連携だ。
Microsoft 365(旧Office 365)は、Windows11を前提としたセキュリティ基盤(TPM 2.0/暗号化通信)上で動作するよう最適化されている。
つまり、Windows10環境では今後、OneDriveとの同期エラーや自動保存の不具合が発生する可能性がある。
さらに、Microsoft 365の利用規約上、サポート外のOS環境での使用は「動作保証の対象外」とされている。
出典:Microsoft Learn – Windows 10でのOfficeサポート(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
また、Officeのセキュリティ更新もWindows Update経由で配信されるため、OSサポート終了後は更新が途絶する。
つまり、Wordは開いても、「安全に文書を扱えないWord」になるということだ。
3-2. YouTube・Netflix・Amazon Prime Video──再生できるけど“止まる日”が来る
次に多いのが、YouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoなどの動画視聴だ。
これもサポート終了直後には動作する。
しかし、問題はブラウザとコーデック(動画を再生する仕組み)の更新が止まること。
たとえば、Google ChromeやMicrosoft Edgeは定期的にDRM(デジタル著作権保護)機能を更新している。
これが更新されないと、YouTube動画が「再生できません」エラーを起こすようになる。
実際、Windows7の終了後、NetflixやAmazon Primeでは再生がブロックされた例が報告されている。
出典:Netflixヘルプセンター – サポートOS情報(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
つまり、動画は動くが、「いつ止まるかわからない地雷原」に足を踏み入れている状態なのだ。
3-3. ネットサーフィン・メール・オンラインサービス──“普通の操作”ほど危険化する
Windows10のサポート終了後、最も危険になるのは、意外にも「ネット閲覧」と「メール」だ。
理由は単純。攻撃者は「古いOSを使っている人」に狙いを定めるからだ。
セキュリティ企業Kasperskyの調査によると、サポート終了OSのユーザーは現行OSに比べ、3倍以上マルウェア感染率が高い(2024年調査)。
出典:Kaspersky公式プレスリリース(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
特に危険なのは、SSL証明書エラーを無視してアクセスする行為や、古いブラウザでネットバンキングを行うことだ。
通信が暗号化されていない状態でID・パスワードを入力すれば、盗聴されるリスクが高まる。
「ネットは見てるだけだから大丈夫」という油断こそ、最も危険な状態だ。
3-4. クラウド・SNS・ショッピング──便利なサービスほど“切り離される”
あなたが普段使っているSNSやクラウドサービス──たとえばX(旧Twitter)、Instagram、Google Drive、Dropboxなど。
これらは常に新しいWebセキュリティ標準(TLS 1.3、OAuth 2.1)で動いている。
古いOSやブラウザでは、それらの仕様に対応できなくなり、ログインできない・画像が表示されないといったトラブルが起こる。
Amazonや楽天などのショッピングサイトでも、支払い画面の暗号化エラーや通信拒否が起きる可能性がある。
つまり、便利さを支える最新技術ほど、古いOSは排除される。
これは「機能を切られる」のではなく、「安全を守るために切り離される」のだ。
3-5. 「個人情報漏洩リスク」は“静かな時限爆弾”
古いOSの最大のリスクは、気づかないうちに情報が抜かれていることだ。
悪意ある広告スクリプト、感染型PDF、改ざんサイト──それらは最新のセキュリティ更新で防げるが、Windows10終了後は防げない。
ブラウザ経由で入力したパスワードや住所、クレジット情報が盗み取られるリスクが高まる。
「被害が出ないから大丈夫」ではない。
むしろ、気づかないうちに情報が売られていることこそが最大の脅威だ。
3-6. まとめ──「まだ動く」は「安全ではない」
- Office製品は動作するが、更新と同期が止まる。
- 動画配信サービスは当面動作するが、再生エラーが発生する可能性が高い。
- ネット閲覧・クラウド・メールは、セキュリティ更新停止で最も危険化する。
- 個人情報の漏洩リスクは時間とともに上昇する。
つまり、サポート終了後も使えるというのは“見かけ上の安定”にすぎない。
「普通の使い方」こそ、最も危険な使い方になる。
次章では、そんな「まだ使える」状況にいる人が、どう判断すべきか──。
Windows10を続けるべきか、それともWindows11へ移行すべきか。
あなたの状況に合った選択肢を、データと比較表で徹底的に整理していく。
Windows10を使い続けるか?買い替えるか?──最適な判断を導く選択肢比較
「まだ動くのに、買い替えるのはもったいない」──誰もがそう思う。
しかし、サポート終了後のWindows10を使い続けることは、単なる節約ではなく、“安全と安心を分割払いで失っていく行為”に近い。
ここでは、Microsoftの一次情報と専門家の見解をもとに、「アップグレード」「延命」「買い替え」という3つの選択肢を、冷静に比較していこう。
4-1. アップグレード・延命・買い替え──3つの現実的ルート
Windows10ユーザーが取りうる選択肢は、主に以下の3通りだ。
| 選択肢 | 内容 | 主な利点 | 注意点・限界 |
|---|---|---|---|
| ① Windows11へのアップグレード | 既存のPCをそのままWindows11に更新 | 最新のセキュリティと機能を維持できる/データを引き継げる | ハードウェア要件(TPM2.0・CPU世代)を満たしていないと不可 |
| ② ESU(拡張セキュリティ更新)で延命 | 有料のセキュリティ更新を追加購入して継続利用 | 一時的にセキュリティを維持できる/猶予期間を確保可能 | 恒久的解決にはならず、機能更新・不具合修正は含まれない |
| ③ 新しいPCへの買い替え | Windows11搭載機に移行 | 長期的な安心・高速化・最新アプリ対応 | 初期コストがかかる/データ移行が必要 |
3つのルートの中で、最も理想的なのは「①アップグレード」だ。
ただし、PCが要件を満たさない場合、ESUで“時間を稼ぐ”か、買い替えを選ぶしかない。
では、その“要件”とは何か。
4-2. Windows11アップグレード要件──あなたのPCは「合格」か?
Windows11を動かすためには、Microsoftが定めたハードウェア条件を満たす必要がある。
参考:Microsoft Docs – Windows 11 要件(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
- CPU: 第8世代Intel Core、Ryzen 2000シリーズ以降
- メモリ: 4GB以上(推奨8GB以上)
- ストレージ: 64GB以上
- TPM(Trusted Platform Module): バージョン2.0必須
- セキュアブート対応: BIOSではなくUEFIモードが必要
これらを一括でチェックするには、Microsoftが提供している「PC 正常性チェック(PC Health Check)」ツールを使うのが確実だ。
出典:PC Health Check App(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
もしこの要件を満たしていない場合、強制的なアップグレードは不可能だ。
つまり、サポート終了後の延命策を検討する必要がある。
4-3. ESU延命策の現実──“時間稼ぎ”ではあるが万能ではない
ESU(Extended Security Updates)は、Microsoftが法人向けに提供してきた有料のセキュリティ延命制度だ。
Windows7終了時には、年間約50〜100ドルで提供されていた。
Windows10版ESUについても、2024年12月に正式発表される予定で、個人ユーザー向け販売も計画されている。
参考:Windows Experience Blog(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
しかし、このプログラムが提供するのは「重大なセキュリティ更新」のみ。
機能追加や不具合修正、ドライバ更新などは一切含まれない。
つまり、ESUは「延命の呼吸」にはなるが、「再生の呪文」ではない。
現実的には、買い替えまでの1〜2年の猶予を得るための制度と考えたほうがよい。
4-4. ハードウェアが古い場合──“安全に使い続ける”のはほぼ不可能
もしあなたのPCが5年以上前のモデルなら、Windows11の要件を満たしていない可能性が高い。
この場合、ESUを契約しても、一部のアプリやサービスはすでに非対応になり始めている。
とくに、Intel第7世代以前のCPUではTPM 2.0チップが搭載されていないことが多く、ハード的に対応が難しい。
それでも「使い続けたい」場合は、ネット接続を極力減らし、オフライン専用機(文書閲覧・印刷用)として利用するのが現実的な選択だ。
だがそれも一時的な策でしかない。
数年後には、アプリやサービスの動作保証が完全に切れる。
「使える」ではなく「守れる」環境に移る──それが長期的に見て最も安上がりな選択なのだ。
4-5. まとめ──あなたの最適解はどれか?
- PCが新しく、要件を満たすなら:Windows11へアップグレード
- 要件を満たさないが、買い替えまでの猶予が必要なら:ESUで延命
- ハードが古い・ネット利用を続けたいなら:買い替え一択
- ネット接続をしない限定用途なら:オフライン専用機として活用
これが、Windows10ユーザーが2025年を迎える前に取れる“現実的な4択”だ。
いま行動するかどうかで、来年以降のリスクがまったく変わる。
「動く」かではなく、「守られるか」で判断せよ。
次章では、個人・会社員・自営業など、仕事の形態によってリスクと判断がどう変わるかを徹底分析する。
あなたの働き方が「継続使用に耐えられるか」を、具体的なシナリオで見ていこう。
仕事(個人・会社員)によって変わるリスクと「継続使用」の考え方
パソコンを「仕事道具」として使っている人にとって、Windows10サポート終了は単なるニュースではない。
それは、仕事の継続可否を左右する“セキュリティ境界線”だ。
同じWindows10でも、「個人利用」と「業務利用」では背負うリスクの質がまったく違う。
ここでは、あなたの職業・働き方に応じて、継続使用の現実的な判断軸を提示する。
5-1. 個人利用──「自己責任」で済む範囲の限界
まず、家でWordやExcelを使ったり、YouTubeを見たりする一般ユーザー。
この層にとって、Windows10サポート終了は「直ちに使えなくなる」ほどの致命傷ではない。
しかし、セキュリティ更新が止まることで、個人情報や金融データを扱う操作(ネットバンキングやショッピングなど)に致命的なリスクが発生する。
ウイルス対策ソフトを最新のまま維持し、VPNを活用することで一定の延命は可能だ。
だが、「自己防衛」に限界があるのも事実だ。
たとえば、2023年に発見された脆弱性「CVE-2023-36884(Office HTML RCE)」は、更新を止めたOS環境では防ぎようがなかった。
参考:Microsoft Security Response Center(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
つまり、「自分だけの利用だから大丈夫」とは言えない時代なのだ。
5-2. 会社員・法人利用──コンプライアンス違反の地雷原
会社のPCがWindows10のまま──これは今後、法令・契約上のリスクをはらむ。
多くの企業では、情報セキュリティ規程で「サポート終了OSの使用禁止」を明文化している。
理由は、1台の古いPCが社内ネットワーク全体の侵入口になるからだ。
IPA(情報処理推進機構)は、サポート終了OSを利用し続けるリスクとして、「標的型攻撃」「マルウェア感染」「サプライチェーン侵害」の3点を警告している。
出典:IPA – サポート終了OS利用の危険性(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
万一、サポート切れPCを介して情報漏洩やウイルス感染が発生した場合、企業は「管理不備」として責任を問われる可能性がある。
しかもそれは「社員個人の責任」では済まない。
契約先企業・取引先に損害が及べば、損害賠償や取引停止にも発展しかねない。
つまり、会社員がWindows10を使い続けるのは、“会社全体の爆弾”を抱える行為なのだ。
5-3. 自営業・フリーランス──顧客データを扱うなら即移行必須
フリーランスや個人事業主も、リスクは会社員と変わらない。
むしろ、顧客データや取引情報を個人PCで扱っている分、漏洩時の責任が直接自分に降りかかる。
とくに業務委託契約や守秘義務契約(NDA)を結んでいる場合、「サポート終了OSを使っていた」というだけで契約違反になることがある。
これは実際に、企業のセキュリティ監査で指摘されたケースも報告されている。
また、クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード等)や電子申告(e-Tax)を利用する際に、古いOSでは接続できない・エラーになる可能性も高い。
「仕事に使う」=「顧客を守る責任がある」。
そう考えれば、サポート終了OSの継続利用は、職業倫理的にも難しいと言わざるを得ない。
5-4. 用途別リスク比較表──“誰がどこまで使えるか”の現実
| 利用形態 | 主な利用内容 | 継続使用の可否 | 主なリスク |
|---|---|---|---|
| 個人利用(家庭・趣味) | Word、動画、ネット閲覧 | 条件付きで可能(限定用途) | 個人情報漏洩、ブラウザ脆弱性 |
| 会社員(業務端末) | 社内ネットワーク、Office業務 | 原則禁止(セキュリティ違反) | 情報漏洩、社内感染、取引停止 |
| 自営業・フリーランス | 顧客データ管理、電子申告 | 非推奨(契約上リスク) | 機密情報流出、信用失墜 |
| 教育機関・医療・行政 | 個人情報処理、記録管理 | 完全禁止(法令・ガイドライン違反) | 法的責任、行政指導 |
この表から明らかなように、「まだ使える」は個人レベルでの話にすぎない。
仕事や取引に関わる以上、Windows10の継続使用は“安全圏外”だ。
あなたのパソコンが、会社の信用・顧客の命綱を握っているという意識を持つことが重要だ。
5-5. まとめ──仕事における「Windows10延命」は自己満足に過ぎない
- 個人利用:限定的な用途なら自己責任で延命可能。
- 会社員:セキュリティポリシー違反リスクが高く、原則禁止。
- フリーランス:契約・信用を守るため、早期移行が現実的。
「まだ使えるから」という感覚は、仕事においては命取りになる。
OSは“道具”ではなく、“信用の基盤”だ。
次章では、いよいよ最終ライン──「この用途の人は絶対にWindows11へ移行すべき」具体的なケースを解説する。
あなたの仕事・生活の中で、どこに“買い替え必須ライン”があるのかを明確に見極めよう。
「この用途ならWindows11以外はNG」──買い替えが避けられない人とは
「本当に買い替えなきゃダメなの?」という質問に対して、私ははっきり答えよう。
──はい、“あなたの使い方”次第では、即時移行が必要だ。
特に、仕事・学習・生活の中で「ネットを介して情報を扱う」人ほど、Windows10継続は危険だ。
ここでは、Windows11搭載PCへの買い替えが“必須レベル”となる具体的な用途と、その理由を整理する。
6-1. オンラインバンキング・確定申告など“金融情報”を扱う人
最も危険なのは、お金に関わる通信を行う人だ。
ネットバンキング、証券取引、確定申告(e-Tax)、ふるさと納税──これらのサービスは、暗号化通信(TLS 1.3)を前提にしている。
Windows10がサポートを終えると、暗号化ライブラリ(Schannel.dllなど)の更新も停止するため、通信の安全性が保証されなくなる。
金融機関の多くは「サポート切れOSでのアクセスを禁止」しており、実際に接続できなくなるケースも出ている。
出典:全国銀行協会:オンラインバンキングの安全利用ガイド(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
つまり、古いOSのままでは「ログインできない」「決済が通らない」などのトラブルが発生する。
お金を扱う人にとって、Windows10の延命は“鍵を壊した金庫をそのまま使う”に等しい。
6-2. Teams・Zoom・SlackなどWeb会議・コラボツールを日常的に使う人
リモートワークの普及により、Web会議やクラウド共同作業が生活の一部になっている。
だがこれらのアプリは、頻繁に暗号化方式・認証プロトコルを更新しており、Windows10サポート終了後は非対応になる可能性が高い。
特にMicrosoft Teamsは、2024年版からWindows11向けに設計を最適化しており、Windows10では機能制限が報告されている。
参考:Microsoft Teams Hardware Requirements(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
ZoomやSlackも同様で、古いOSでは暗号化通信や画面共有機能が不安定になる可能性がある。
「音声が途切れる」「画面が映らない」──それは単なる通信不良ではなく、OS老化の兆候かもしれない。
6-3. 教育・医療・行政など、情報保護基準が厳しい分野で働く人
学校・病院・自治体などでは、OSのサポート状況は法令やガイドラインで明確に定められている。
文部科学省のGIGAスクール構想、厚生労働省の医療情報システム安全管理指針、総務省の自治体情報セキュリティ対策ガイドライン。
これらはすべて、「サポートが終了したOSを業務利用してはならない」と明記している。
参考:総務省:自治体情報セキュリティ対策検討チーム報告書(PDF)(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
医療機関では、カルテや検査データを扱う端末が攻撃された場合、個人情報保護法違反として処分対象となる。
教育現場でも、生徒情報を管理する端末がWindows10のままだと、教育委員会の監査で使用停止になる可能性がある。
つまり、これらの分野では「まだ動く」以前に、「使ってはいけない」のである。
6-4. セキュリティ基準が厳しい企業・業界に所属している人
金融・製造・ITベンダー・通信業界では、社内システムのセキュリティ基準が特に厳しい。
これらの業界ではISO/IEC 27001やNIST SP800シリーズなどの国際基準に準拠しており、サポート終了OSを接続すること自体が監査対象になる。
たとえば、社内VPNがWindows10端末からの接続を遮断する設定に変わる企業も出てきている。
つまり、Windows10を使い続けるという選択は、「仕事の入り口を自ら閉ざす」可能性がある。
6-5. “買い替え判断”チェックリスト──あなたはいくつ当てはまる?
以下の項目に2つ以上当てはまるなら、Windows11搭載PCへの移行を強く推奨する。
- オンラインバンキングや確定申告を行う
- Teams/Zoom/Slackなどを日常的に利用している
- 顧客・生徒・患者などの個人情報を扱う
- 会社や組織のネットワークに接続している
- Microsoft 365を使用している
- クラウドサービス(Google Drive・Dropbox等)を使っている
- 取引先や契約で「セキュリティ条件」がある
- PCが5年以上前のモデル
3つ以上当てはまる場合、Windows10の延命は“リスク延長”でしかない。
「まだ使える」は、もう安全の証明にはならない。
6-6. まとめ──「買い替え」は出費ではなく“未来への保険”
- 金融・教育・医療・行政など、高リスク領域の人は即時移行が必須。
- Teamsやクラウド利用者も、Windows11への移行が最も安全。
- 古いPCを延命するほど、後で発生するトラブルコストは高くつく。
新しいPCは「贅沢」ではなく、「自分と周囲を守るセーフティネット」だ。
“更新が止まるOS”を守る術はない。
今、動く勇気があなたとデータを救う。
次章では、Windows10ユーザーが“今すぐできる安全対策”と、“スムーズな移行ロードマップ”を紹介する。
「まだ間に合う行動リスト」を一緒に確認していこう。
今すぐできる「安全対策」とWindows11への移行ロードマップ
「わかってはいるけど、何から始めればいいのかわからない」──多くの人がそう感じている。
でも安心してほしい。
Windows10ユーザーが今日から取れる安全対策と、Windows11移行までのステップは、実は明確だ。
ここでは、専門知識がなくてもできる“現実的な防御と準備”を、手順付きで解説する。
7-1. まずやるべきは「バックアップ」──失ってからでは遅い
最初にやるべきことは、全データのバックアップだ。
OS移行や買い替えを行う際、最も多いトラブルが「写真・文書が消えた」というもの。
外付けHDD/SSD、またはクラウド(OneDrive・Google Driveなど)に必ず保存しておこう。
特に重要なのは次の5項目だ。
- ① ドキュメントフォルダ(Word/Excelデータ)
- ② デスクトップ上のファイル
- ③ 写真・動画・音声データ
- ④ メールのデータ(Outlookなど)
- ⑤ ブラウザのブックマーク・パスワード
これらを外部ストレージにコピーし、「PCが壊れても復元できる状態」を作ることが、最初の防御線だ。
7-2. 自分のPCがWindows11対応かチェックする
次に、あなたのPCがWindows11にアップグレード可能かを確認する。
Microsoft公式の「PC 正常性チェック(PC Health Check)」ツールを使えば、ボタン1つで判定できる。
出典:PC Health Check App(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
もし「このPCはWindows11の要件を満たしていません」と表示されたら、買い替えを前提に検討しよう。
ただし、メモリ増設やTPMモジュールの追加で対応できるケースもある。
PCショップやメーカーのサポートページで、自分のモデルが対応しているか調べてみるのも有効だ。
7-3. Windows10を安全に使い続けるための5つの防御策
どうしてもすぐに移行できない人は、次の5つの対策を実施して“リスクを最小化”しよう。
- ① ウイルス対策ソフトを最新状態に保つ(Microsoft Defender または市販製品)
- ② 不要なソフト・スタートアップを削除(脆弱性を減らす)
- ③ メール添付・リンクを安易に開かない(フィッシング防止)
- ④ 管理者権限の利用を減らす(感染拡大を防止)
- ⑤ VPNを活用し通信経路を暗号化(公衆Wi-Fi利用時は特に必須)
ただし、これらはあくまで「延命策」だ。
OSそのものの脆弱性を修復することはできない。
つまり、これらを行ったうえで“移行計画”を並行して進めることが重要だ。
7-4. Windows11移行のロードマップ──3ステップで完了
移行作業は面倒に思えるが、実際は次の3ステップで完了する。
- STEP 1:バックアップを取る(前述の手順)
- STEP 2:Windows11のインストールメディアを作成(USBまたはISO形式)
- STEP 3:アップグレード実行 or 新PCへデータ移行
Microsoft公式の「Windows 11 インストールアシスタント」なら、クリック操作で自動アップグレードも可能だ。
参考:Microsoft公式 – Windows 11 ダウンロード(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)。
また、新しいPCを購入する場合は、初回セットアップ時にMicrosoftアカウントでサインインすれば、OneDrive経由でデータが自動復元される。
「面倒」よりも「守る」が先。 この3ステップを済ませれば、あなたのPC環境は次の10年も安全に使い続けられる。
7-5. 買い替え時に後悔しないためのチェックポイント
もし新しいPCを購入する場合は、以下の5つの視点で選ぶと失敗がない。
- ① CPU: 第12世代Intel CoreまたはRyzen 7000シリーズ以降(AI支援機能に対応)
- ② メモリ: 16GB以上推奨(Office+ブラウザ作業に快適)
- ③ ストレージ: SSD(NVMe)で512GB以上
- ④ ディスプレイ: フルHD以上+ブルーライト軽減機能
- ⑤ 保証期間・サポート体制: メーカー保証1年以上+オンライン修理受付
特に「仕事でも使う」人は、サポートの早い国内メーカー機か、法人モデル(NEC・HP・DELL Proなど)を選ぶと安心だ。
AI支援(Copilot)やクラウド連携を前提に考えるなら、Windows11世代への早期移行はむしろ投資に近い。
7-6. まとめ──行動すれば“守れる未来”はすぐ作れる
- まずはバックアップ、そしてPCの対応確認。
- 移行までの間も、5つの防御策でリスクを最小化。
- Windows11移行は3ステップで完結。迷うより先に動く。
たとえ今日アップグレードしなくても、「準備」を始めることであなたのデータは守れる。
最悪なのは、何もせずに2025年10月14日を迎えること。
行動した人から、“安心”を手に入れられる。
次章では、この記事の総まとめとして──
仕事・家庭・個人利用それぞれに向けた「移行戦略マップ」を紹介し、次の記事への導線を提示する。
あなたが今どの段階にいるか、そしてどこへ進むべきか。その“判断の地図”を広げよう。
FAQ(よくある質問)
Q1. Windows10は2025年10月14日以降も使えますか?
はい、起動自体は可能です。ただし、セキュリティ更新が完全に停止し、ウイルス感染や情報漏洩のリスクが急増します。
Q2. Windows10を安全に使い続ける方法はありますか?
Microsoftの拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)を契約すれば、最大3年間の延命が可能です。ただし、恒久策ではなく“時間稼ぎ”です。
Q3. 買い替えせずにWindows11にアップグレードできますか?
PCがTPM2.0・UEFI・第8世代以降のCPUなどの要件を満たせば可能です。Microsoft公式の「PC正常性チェック」ツールで確認してください。
Q4. 動画配信やYouTubeはいつまで使えますか?
短期的には再生可能ですが、ブラウザやコーデック更新が止まるため、数か月~1年以内に再生エラーが増える見込みです。
Q5. Windows10を仕事で使い続けるのは問題ですか?
はい。企業・行政・医療などの環境では法的・契約的リスクがあります。業務用途ではWindows11環境への移行が必須です。
Q6. 新しいPCを選ぶときのポイントは?
CPUは第12世代Intel Core以上、メモリ16GB以上、SSD512GB以上を推奨します。AI支援機能やクラウド対応を考慮すれば長期的に安心です。
更新履歴: 2025年10月07日(JST) 初版公開| 以後、Microsoft発表・政策変更時に内容を逐次更新予定。
最後に── サポート終了は“終わり”ではない。
それは、あなたのデジタル生活を再設計するためのタイミングだ。
今日動けば、2025年10月14日は恐怖ではなく、「新しい安心の始まり」になる。
参考・参照元
- Microsoft公式 — Windows10 サポート終了日のお知らせ(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- Microsoft公式ブログ — How to Prepare for Windows10 End of Support(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- Microsoft Docs — Windows 11 要件(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- Microsoft Security Response Center — CVE-2019-0708 BlueKeep 脆弱性(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- IPA(情報処理推進機構) — サポート終了OSの利用リスクについて(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- 経済産業省 — サイバーセキュリティ経営ガイドライン(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- 全国銀行協会 — オンラインバンキングの安全利用ガイド(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- Netflix公式ヘルプ — Netflix 動作サポート環境(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- Kaspersky公式 — サポート終了OSのリスクに関する調査レポート(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)
- 総務省 — 自治体情報セキュリティ対策検討チーム報告書(PDF)(最終閲覧日:2025年10月07日 JST)